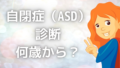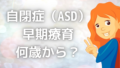「新生児の息子。
反り返りが強くて
抱っこもしづらいです。
抱っこが嫌なのかも?
とも感じる今日この頃。
反り返りが強いと
「自閉スペクトラム症(自閉症・ASD)」の
疑いもあると聞きました。
「自閉スペクトラム症(自閉症・ASD)」のお子さん
反り返りはありましたか?」

こんにちは。
型破りママ☆レイコです。
シングルマザーでも
・海外に住みながら
・自閉症の息子ミスタームーン
・ADHDの娘ミスサンシャイン
子ども達とタッグを組んで
人生を冒険中!
今回のそのお悩み、「レイコ白書」にまとめました。
レイコの海外生活より
・「自閉スペクトラム症(自閉症・ASD)」新生児の「反り返り」は自閉症サイン?【エピソード】
についてお届けします。
【この記事で学べること】
・「自閉スペクトラム症(自閉症・ASD)」の息子の新生児期「反り返り」にまつわるエピソード【体が硬かった】
お子さんが
新生児の場合
不快な気持ちを表す
意志表示の1つとして
「反り返って」嫌がる。
という状況が
あるかと思います。
たとえば
赤ちゃんは
抱っこされるとき
姿勢が気に入らなかったり
居心地が悪かったりすると
「嫌がる」感情を表現するために
「反り返る」。
「反り返る」は
「のけ反る」かたち
なのですが
エビのように
丸まった形を連想したり
アイススケートの
イナバウアーのような姿勢
を思い浮かべてみた時に
「自閉スペクトラム症(自閉症・ASD)」の息子
ミスタームーンの幼少期
果たして
そのような「反り返り」が
頻繁にあったのか?
「自閉スペクトラム症(自閉症・ASD)」であることと
「反り返り」には関連がある?
この背景から記事を書きます。
「自閉スペクトラム症(自閉症・ASD)」の息子(新生児)「反り返り」にまつわるエピソード

「自閉スペクトラム症(自閉症・ASD)」の息子
ミスタームーンの新生児期
「反り返り」というキーワードから
「自閉スペクトラム症(自閉症・ASD)」を疑った
記憶はありません。
ただ
・体が硬い
・体が強い
・体の抵抗感が半端ない
こう感じた印象が
確かにあって
これは
「反り返り」が
おこりやすくなる要素
「筋肉がこわばっている」
ここに
共通点があるのでは?
と考察します。
「自閉スペクトラム症(自閉症・ASD)」の息子(新生児)実際に新生児の「反り返り」はあったのか?
「自閉スペクトラム症(自閉症・ASD)」の息子が
新生児だったとき
まだ起き上がることが
できない月齢で
明らかに
エビのような形で
布団の上で
反り返ったりしていた印象は
ありません。
でも
「抱っこされる」ことに関連する
特有のエピソード
ならしっかり存在していて
「反り返り」を誘発する
「筋肉のこわばり」
この要因が
何らかの形で
「抱っこされる」時におこった
ある癖に
反映されていたのでは?
と感じています。
「自閉スペクトラム症(自閉症・ASD)」の息子の新生児期、「抱っこ」をするとき、ストンと腕の中に納まってくれる感がなかったのです。「ピーンと真っすぐな感じ」が母の腕の湾曲にフィットしない。これが息子の「抱っこ」でした。
「自閉スペクトラム症(自閉症・ASD)」の息子(新生児)「反り返り」ではなくても実は関係ある?抱っこされるときの癖【ベビーキャリーエピソード】
「自閉スペクトラム症(自閉症・ASD)」の息子
ミスタームーンの新生児期。
・後ろに強くのけぞる姿勢が多い
・ずっとのけぞった姿勢でいる
このような
「反り返り」はなかったものの
「抱っこ」に
ひと癖・ふた癖ありました。
【ベビーキャリーのエピソード】
「新生児対応」のベビーキャリーを使用して、息子ミスタームーンを前に抱っこ。これが外出する際の定番スタイル。当時、レイコにとっては非常にストレスフルで、印象に残っているエピソード。それは、とにかくレイコが「歩きにくかったこと」。
ベビーキャリーを使うと、赤ちゃんとお母さんが向き合う形で密着、赤ちゃんの足はだら~んと下にぶら下がっている状態です。ほとんどの場合、たいていの赤ちゃん、抱っこされると、安心してリラックス。足も力なく、だら~んとぶら下げている。こういう状態だと思うのです(少なくともレイコの第一子、娘ミスサンシャインの抱っこはそうでした)。
「自閉スペクトラム症(自閉症・ASD)」の息子(新生児)の場合、ベビーキャリーで抱っこをしている間、リラックスして安心モードは皆無。
ずーっとレイコの脚の付け根部分を、力いっぱい蹴り返してくるんです。これがホントに「ずーっと」。
一歩を踏み出すたびに、まだ小さい足の裏が、でもしっかりと力をこめて、反発するように蹴ってくる。レイコにとって、ベビーキャリーを使って「歩く」が非常に苦痛でした。
「自閉スペクトラム症(自閉症・ASD)」の息子(新生児)「反り返り」は嫌な気持ちの表れ【筋肉がこわばるという状態】
「自閉スペクトラム症(自閉症・ASD)」の息子
ミスタームーンの新生児期。
抱っこのカタチや姿勢が
気に入らない
そんな場合にも
「反り返り」
という反応で
嫌な気持ちを
新生児が表現する場合が
があるでしょう。
居心地が悪い状態に対して
反射的に筋肉をこわばらせて
「反り返る」
なのだとしたら
「自閉スペクトラム症(自閉症・ASD)」の息子
ミスタームーンの場合
常に
「筋肉がこわばった状態」で
抱っこされた状態でも
「体が硬かった」。
逆に
「体が硬かった」からこそ
・新生児の息子の身体を
抱き上げる時
逆に
・ベビーキャリーから
降ろす時には
独特な
「力強さ」
(=筋肉のこわばり)が
赤ちゃん自らに
備わっているので
新生児の身体を
扱う側(レイコ)は
「おっ、体が強い。自立感があってすごいな。」(さすが、男の子はちがうもんだ)
なんて
感じていたほど。
今振り返れば、「自閉スペクトラム症(自閉症・ASD)」の息子の新生児期、反発されるようにレイコの足の付け根を蹴られ続けてベビーキャリーで抱っこをしたり、抱っこをすること自体に妙な(新生児らしからぬ)安定感があったのは、本来はもっと力を抜いていいところで、「体の筋肉が緊張した状態にあった」、息子の特徴的な体の状態の1つだったのだと思うのです。
「自閉スペクトラム症(自閉症・ASD)」の息子(幼少期)実際にあった「反り返り」【癇癪とセット】
「自閉スペクトラム症(自閉症・ASD)」の息子
ミスタームーンが「反り返り」
エビのカタチのように
「反り返る」
が起こったのは
彼の「幼少期」で
息子の「怒」
を表す手段の1つ
でした。
「自閉スペクトラム症(自閉症・ASD)」の息子は、「癇癪」がひどく、幼少期は「反り返り」も積極的に取り入れて「怒り癇癪」を爆発させました。
これは
「筋肉のこわばり」でも
なんでもなく
息子の「怒」
のけ反って
「怒る」です。
「自閉スペクトラム症(自閉症・ASD)」の息子(現在小学生)「反り返り」はなくても身体が「鉄板」のように固い件【就寝時】
「自閉スペクトラム症(自閉症・ASD)」の息子
小学生の現在
かつては
毎度毎度の
「癇癪」とセットの「反り返り」も
なりをひそめ(←療育の成果+本人の成長)
もう息子は
小学生なので
もちろん
「抱っこ」して運ぶ
もありません。
ですが
「筋肉のこわばり」に
共通する要素が
今でも確かにある。
と顕著に感じる場面は
「就寝時」。
お子さんの寝相が悪い場面。想像してください。お布団から飛び出しているってなれば体のポジションをなおしてあげる。となりますよね。この時、親は子どもの体を軽く持ち上げるはずです。
「自閉スペクトラム症(自閉症・ASD)」の息子、ミスタームーンに、このアシストをするとき、もうびっくりするほど「体、硬っ!」ってびっくりします!
体の真ん中に、厚さ10㎝はある鉄板が、頭の先から足のつま先まで入ってるんじゃないのか。。。って疑いたくなるぐらい、「ピーンと体が真っすぐ硬い!」
息子はぐっすり就寝中、体を持ち上げたって起きません。でも体は「超硬い」、真っすぐに鉄板が入ったような、加えて、余計に重く感じる小学生の体を、寝相の悪さを直すために、グググッッ!と力をいれて持ち上げます。
レイコは
感じます。
「自閉スペクトラム症(自閉症・ASD)」の子どもって
やっぱり
「自分の体に対する力のいれかた」に
独特な要素がある。
これは
「自閉スペクトラム症(自閉症・ASD)」
であるが故
さまざまなセンサリー(五感)が
敏感で
想像もしない些細な事が
・見えたり
・聞こえたり
・感じたりの
大きな刺激となっていて
常に
体に「力をいれている」
こうなのかも知れない。
そう感じます。
「寝ている時」でさえ、あんなに硬い。体も心も休まっているのだろうか。と少し心配です。
まとめ
今回のレイコ白書は
「自閉スペクトラム症(自閉症・ASD)」新生児の「反り返り」は自閉症サイン?【エピソード】
・「自閉スペクトラム症(自閉症・ASD)」の息子 新生児「反り返り」にまつわるエピソード【体が硬かった】
について
お届けしました。
「自閉スペクトラム症(自閉症・ASD)」の息子
ミスタームーンが
新生児だったとき
「自閉スペクトラム症(自閉症・ASD)」
を疑う要素として
「反り返り」があったのか?
ここを
考察してみた
今回のエピソード。
息子ミスタームーンの場合
「反り返り」という
言葉そのものよりも
「反り返り」にも通ずる
・「筋肉のこわばり」
・「体の硬さ」
このあたりが
「自閉スペクトラム症(自閉症・ASD)」である
子どもの特徴の1つ
だったのかもしれない。
そのように
感じています。
現在の息子の体も
「力のいれかた」には
依然
独特なものがある。
もし
まだ新生児のお子さんの
体の様子が
・のけ反る姿勢が極端に多い
・体が異様に緊張している
・手足のうごきがぎこちない
などと感じる場合は
もしかしたら?
と予防線をはって
必要に応じて
早めにお子さんが必要とするサポートを
提供する。
が大切です。
願わくば
多くの新生児の赤ちゃんが
極度に緊張をすることなく
「体をリラックスさせることができる」
そんな環境で
スクスクと成長できますように。